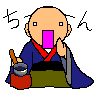【タマゴ】
同じ種類でなくても、ポケモンは交尾し、種族を残すことが出来る。
産まれるのは全てメスと同じ種類のポケモンであり、親から技を受け継ぐこともある。
また、全てのポケモンが産まれるのはタマゴから決まっており、
なぜ別の方法が無いのか、学者たちの間で議論を巻き起こしている。
PAGE44.降ってきた
太陽の代わりに、星が2人の影を作りだした。
鼻先をなでる冷たい風は サファイアの汗を奪っていく。
「・・・・・・っぁ〜・・・」
サファイアは擦り剥いた(すりむいた)指先を口でくわえると 流れた血を吐き出した。
何度反撃のチャンスをうかがっても、スキらしきものの1つも見つからず、攻撃が加えられない。
だが、サファイアとてやられっぱなしで黙っているつもりもない、
変わらない笑顔で じっとサファイアのことを見つめているコハクをにらみ返すと、立ち上がってカナの様子を用心深く観察した。
足元がしっかりしている、まだ戦うことは出来そうだ。
「・・・カ・・・・・・!!」
指示を出そうと口を開いた途端、上空から次々と何かが降ってきてサファイアは身をすくませる。
今さっき立ち上がろうとしたばかりなのに また尻もちをついた彼の目の前に 赤いペンキのようなもので大きく『×』と描かれた岩が ふんぞり返った。
「コハク・・・ワシのことバカにしとるんか・・・?」
軽く首を横に振ると、足音もほとんど響かないような足取りでコハクは段々と近寄ってくる。
いつもとほとんど変わらない笑顔に殺気を感じ、逃げようとサファイアが体を動かすと、どん、という音を立てて背中から何か壁のようなものにぶつかった。
サファイアが後ろを振り返ると、山のようにそびえ立った『×』印のついた岩が 逃げ道を完全に封鎖している。
よく1つも当たらなかったものだ、と一瞬感心もしたが、すぐにそれ以上の事態の重さに気付いた。
あちこち動きまわってようやく決定打を避けていたカナとサファイアが、動きを制限されるということ。
後ろ手で岩を叩き、コハクを睨んで歯を食いしばる。
「・・・なんでや・・・・・・?」
まっすぐに瞳を見つめたまま、サファイアは声を荒げずにコハクへと話しかける。
素直に立ち止まり、金色のくりくりとした瞳でサファイアのことを見つめる少年へと口を動かすと、自然と心が落ち着いてきた。
パクパクさせていた口を1度閉じ、合わせていた視線を落として足元を見つめ、唾(つばき)を飲み込んで頭の中で話を整理する。
「1回も勝てひんのも悔しいわ。
頑張っても、なんべんレベル上げても、ルビーにもコハクにもメノウにもスザクにも、アクア団にもマグマ団にも勝てひん。
でもな、何で今戦っとんのかも分からへんねん。 なんで、ワシ、コハクと戦っとんの?」
サファイアが顔を上げると、コハクは見たこともないような、太陽のような笑顔で笑っていた。
口をぱくぱくと動かし、ゆっくりとサファイアへと近づいてくる。 背後の空はすっかり闇がおおいつくし、いくら探しても本物の太陽の姿は見えない。
代わりに、星が2人の影を作りだした。
鼻先をなでる冷たい風は サファイアの汗を奪っていく。
「・・・・・・コハク?」
あれだけ殺気だっていたコハクは しゃがみこんで、サファイアのひたいに手を当てていた。
ひやんとした感触に思わずサファイアが目をつぶると、落ち付きかけていた心臓が1つ、トクン と、鳴る。
うっすらと、小さく瞳を開くと、コハクはいつもの顔でニコニコと笑い、人差し指で上を指差していた。
それに合わせてサファイアが顔を上げると、あれほど暗かった空が光を帯び始めている。
驚いて目を見開くと、空が一瞬カメラのフラッシュのように光り輝いた。 反射的に目をつぶったサファイアの下っ腹に 何か重いものがのしかかる。
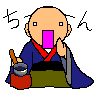
事態を察知したのか、コハクらしき手によって『重いもの』は取り上げられた。
声を出すことも出来ず、サファイアは じたばたごろごろと転げまわる。 痛い、かなり痛い場所に落下されてしまった。
真っ正面のN(エヌ)の落とした岩に頭をぶつけ、ようやくうめくことを思い出す。
「〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ッ〜〜!!? ・・・・・・ひぅぅ〜〜〜〜〜・・・・・・!!・・・」
ぼたぼたと涙を落とすサファイアを止めるような人間はいなかった。
思う存分、痛みを満喫し、まだなお残る苦痛と必死に格闘しながら、コハクの方へと顔を上げる。
コハクは 笑うべきなのか心配するべきなのか困りかねているような、複雑な表情をしながら、手にした落ちてきた重いものをサファイアへと差し出した。
渡されたら受け取ったる。 サファイアは反射的に重くて硬いものを両腕で抱きかかえると、コハクの顔をもう1度見直そうと顔を上げる。
その前に自分の体が横たわったことには、気付かなかった。
全ての思考が、『でんじは』のマヒ効果によって、止められていたのだから。
「ねぇ、1つ聞いてもいい? どうしてトレーナーになったの?」
ルビーを自分のベッドで寝かせ、机の上で何か書き物をしながらスザクは唐突に尋ねてきた。
ちなみに、食事の時間を過ぎてもサファイアが戻ってこなかったことに関しては、2人ともあまり気にしていないらしい。
借り物のゆったりした服でふかふかのベッドの上をごろんと転がると、ルビーはすっかりカラカラになった髪を指先で遊ばせる。
かなり小さな声で何かを言うが、とてもじゃないが聞き取れない。
ペンを止めて回転椅子をぐるりと動かすと、スザクはごろごろとルビーの元へと寄ってきた。
「聞きたいなぁ。」
ルビーは視線をそらすが、それでもスザクの真っ直ぐな視線が自分へと向けられていることが判る。
幾度となく「聞きたいな」コールが続くと、ルビーは諦めたようにため息を1つついた。
「その場の勢いだよ なりたくなんてなかったよ 気がついたらトレーナーにされてたんだよ!!」
かなり投げやりな言葉がポンポンと飛んでくる。
何を思ったのかも判らないが、ルビーが横目でスザクのことを見ると、彼女はきょとん、と コハクとまるで同じリアクションを取っている。
気付かれないようにまた視線をスザクから離すと、キャスターの転がるコロコロッという音が耳をつく。
ため息をつこうかと考え始めたとき、先に息の吐かれる音が聞こえ、ルビーはタイミングを失った。
「もしかして、ルビー・・・・・・・・・ポケモン嫌い?」
「・・・あぁそうだよ、嫌いだよ。 だから何か?」
ほんの少し困ったような顔をして、スザクは天井を見上げてみる。
指先でくるくるとペンを回し、小さくふぅ、と息をついた。
「そっか、いるんだよね〜、ホントに稀(まれ)に。 ポケモン嫌いのトレーナー。
『そういう』子に限ってバトルの才能があったりして・・・あ、ルビーもそうか・・・・・・
ねぇ、帰りたいって思うの、やっぱ?」
「・・・帰るトコなんてないよ、家出してきたんだ。」
「淋しい?」
「スザク・・・・・・」
「?」
「質問が多くて、うっとうしいって言われたことないかい?」
「・・・ある。 でも、これが『あたし』だから。」
ほぼ即答するとスザクは何かを書き終えたらしく、本の間にペンをはさみ、畳んだ。
しっかりとクセのついている髪をひとまとめにすると、蛍光灯の明かりを落とし、「おやすみ」の呪文を唱える。
『じゃーんけーん・・・・・・・・・・』
「ぽんっ!!」
と、出された8つの手は、バラバラな形をしていた。
それで複雑な顔をしたのは、1人、2人・・・
「ヘムさん〜、グーパーって言ったじゃないですか・・・
何でチョキを出すんです・・・」
握りこぶしから人差し指と中指が突き出た手を、医療学生ヘムロックは「あら」と言いながら見直した。
そして、隣の黒尽くめの女医療学生、レインに視線を移す。
「霧崎さんは、ずいぶん不思議なことしてるんですね。」
「じゃんけんの本場では剣と盾を使って勝敗を決めたそうです。 成川さんは何をなさっているのでしょう?」
「だっておめぇ、ジャンケンつったらウルトラじゃんけんに決まってだろ?
レサシは何やってんだ、いきなり走り出したりして・・・」
「ごめん、マリルが突然騒ぎ出したんだ。
アルムもまた、ずいぶんと変わったことやってるな・・・・・・」
右手でグー、左手でチョキ、足でパーを出しっぱなしのポケモン医研修生アルムは、首を傾げると固めていた手足を元に戻した。
仮のリーダーをつとめていた医療学生ヒデピラは ため息を1つつく。
「これですと、いつまで経っても決まりませんね。
やはり、希望者のみを募った(つのった)方が早いのではないでしょうか?」
細身のメガネを直しながら、看護学生のマキは言った。
彼らが研修している病院から患者であるミツルが抜け出してから1日半、なぜかそれだけ時間が経ってから、なぜか研修生たちに捜索の指令が出されている。
理不尽(りふじん)だ、という声もあがったのだが、
そこは何とかヒデピラが取り止め、彼を仮のリーダーとして今誰が探しに行くかの班分けを行っているというわけだ。
「で、で、ですが・・・やはり8人しかいないわけですし、やはり組み分けが必要なのでは・・・?
同じ科の人同士が一緒になりますと、患者さんに負担がかかりますし・・・」
「分かった分かった、分かりました。 だったら、2人1組でじゃんけんにしましょう。
みんなじゃんけんは判ってるみたいですから、それで丁度(ちょうど)4人ずつに分けられる。」
ようやくその意見で収まりがついて、同じポケモン医療科のヒイズとアルム同士をじゃんけんさせ、ようやく4人ずつの組が出来あがる。
そこまでにおよそ30分、ヒデピラはため息をつく。
出来るだけ早く見つけなければ、どこで迷子になっているか予想もつかなくなってしまうというのに。
「うわああぁぁぁっ!!?」
何度目だろう、あいと出会ってからミツルが叫ぶのは。
転がって転がってひたすら転がって、長い坂道をミツルにあい、それに新しい仲間のゴニョニョは転げ落ちていく。
どうして森のなかに落とし穴があったりするのか、なんて考えたりする余裕もない。
暗くて視界は利かなかったし、ポケモンたちがいるとはいえ不安はいっぱいだし、夜通し歩いてお腹は空いているし。
数メートルほど転げ落ちたところで、ようやく水平な床の上に到達して1人と2匹は停止した。
「・・・・・・うぅ・・・」
置きあがってはみるが、目が回ってすぐに立てる状態ではない。
きっと、ルビーやサファイア、コハクみたいな人なら、これくらい何ともないんだろうと思ってみると、自分に軽く腹が立つ。
あいに軽く叩かれて自分の顔がゆがんでいることに気付くと、慌てて何でもないような素振りをして、ふらつく足で立ちあがった。
だが、すぐに立ちくらみを起こし、周囲を見る余裕すらうかがえない。
1度座り直し、落ち付くのを待つと、ミツルはもう1度立ちあがった。
あまりしっかり歩ける状態でもないのだが、立ち止まっているわけにもいかない。
「・・・ヒドイ目にあいましたね・・・・・・まさか、森の底が抜けるなんて・・・・・・
ここ、どこなんでしょう・・・あい、それに・・・ゴニョニョの・・・」
言おうとして、ミツルは自分のゴニョニョに名前がついていないことに気がついた。
少し考えるようにすると、しゃがんで視線の高さを少しでも合わせ、ミツルはハラヘリで座り込んでいるゴニョニョに右手を差し出す。
「ゴニョニョの、『ぺぽ』、ここがどこだか、判りませんか?」
空気のかすれるような音がして、ゴニョニョが軽く体をかしげたが、すぐにそれが横に振られ『NO』の合図だということが判明した。
小さくため息をつくと、今度はミツルが首を横にかしげた。
「困ったなぁ・・・とにかく街に行かないと、ボクだって体力が持ちそうにないのに・・・
・・・それ以前に、現在位置も判らないなんて・・・・・・」
「ここより、右に3歩、前に2歩進めば、そこはステキな・・・・・・」
「かっらくっり やぁ〜しきぃ〜〜!!!」
「ぎゃああぁぁぁっ!!?」
旅をしていたら、いつ心臓が止まってもおかしくないな、と その時ミツルは覚悟したらしい。
上から変態まがいの中年男が降ってきて ミツルは天地がひっくり返りそうになるほどの叫び声を上げる。
ぺぽと名付けられたゴニョニョも大声で泣き出して、ミツルチーム、大パニック。
「ようこそ、我が輩(わがはい)が・・・・・・」
「ギャピイィィッ!!」
「ぺぽ、落ち付いて下さい、怪しい人だったら戦えばいいんです!!」
「3ヶ月と1週間と2日かけて作った・・・・・・」
「ギャアァァァッ!!」
「騒いでいたら・・・そうだ、騒げば人が見つけ・・く・・・かも・・・(かき消されて聞き取れない)」
「・・・『からくり屋敷』・・・・・・へ・・・
ええい、だ・・・らっ・・・い!!・・・・・・・・・」
「うるさいっ、あい、『ねんりき』!!」
まだ、何もしていないというのに、話の成り行きだけで謎の中年男(手作りらしい王冠つき)は あいの『ねんりき』で壁側まで吹き飛ばされる。
何とかなだめすかしてゴニョニョのぺぽを落ち付かせると、ごちゃごちゃした部屋は静寂そのもの。
シーン、という効果音が響き渡りそうなほどだ。
その静かな空間を押しのけたのが、ミツルとあいとぺぽ、3つ分しっかりとハーモニーを奏でた(かなでた)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・腹の、音。
「・・・にょここ・・・・・・」
「おなか、空きましたね・・・・・・」
風のかすれるような声を出し、ミツルはしゃがみ込んでお腹を押さえるポーズを取った。
乱雑に物の置かれている部屋の中に小さな冷蔵庫を見付けると、一時黙ってポンと手を打ち倒れている中年男へと歩み寄る。
ポケモン2匹ともども、ちょこんとしゃがみ込むと、うっすらと目を開けた中年男をおびえもせずに見つめた。
「うぅっ・・・なんだかよく判らんが、こんなジジイを心配してくれてるのか、ありが・・・」
「おじさん、ボクたち、おなか空いてるんです。」
床が洪水になりそうなほど涙を落とし、中年男はミツルが見付けた冷蔵庫を指差す。
ミツルたちが素直に指先の冷蔵庫へと向かうのを見届けると、男はいっそう涙の中に埋まった。
もちろん、誰にも気にされることもないのだが。
「・・・ふんふん、なんほど?
とどのつまり、おまいさんはその『ポケモン図鑑』の言うことを聞いて、ここまでふらふらと迷い込んだっちゅうんだな?」
腹減りに任せてポケモンと一緒に久しぶりの(数時間しか経っていないのだが)食事をがっつくミツルから、中年男は 何とかここまでの話を聞き出した。
これだけ勢い任せに食事を取るのは何年ぶりだろう、そんな考えを持ちつつ、ミツルは目だけでパッと見怪しげな男を見る。
「だって、もう病気じゃないんです。
すごく息が切れていたのに、走れるようになったし、痰(たん)も出なくなったし・・・それに、ずっと旅したかったんです。
警察に通報しても結構ですが、ボク、出来るところまで逃げ切るつもりです。」
最後の1口を飲み込むと、ひざに置いた手を握り締めながらミツルは口を動かした。
すっかり腹を満たしたあいとぺぽも それに同意するように男を刺すような視線で睨み付ける。
男は見た目にも似合わず、ほんの少しばかり真剣な表情で考えるようにすると、あぐらををかいていたひざを叩いて立ちあがった。
「ま、病気じゃないならそんなに急ぐこともないであろう、今晩は我が輩の屋敷に泊めてやるから、ゆっくりと休むがよい。
いいか、泊めてのは我が輩の屋敷だからな、わ〜が〜は〜い〜のっ!!」
「はぃ・・・それでは、お言葉に甘えて泊めさせていただきます、我が輩さん。」
「我が輩は、からくり大王である、からくり大王・・・」
彼らは見えないのだが、空を見上げれば降るような星空。
野生のポケモンよりも静かな足音でポケモンセンターを抜け出してきたメノウは、その空へと向かって小さく息をつく。
なんとなく、眠れないだけ。 だが、ベッドの上でじっとしていることも出来ない。
体を動かせばおさまるかとも考えたのだが、今夜は眠ることを許してくれないだろう。
顔にかかる赤い髪を背中へと回すと、まぶたの下の銀色の瞳を空へ向け、星へと向かってか、つぶやいた。
「・・・・・・ったく、どこ行ってんだよ・・・あいつら・・・・・・」
<ページをめくる>
<目次に戻る>